オールド・ワールドの黎明期から、カール・フランツ帝の治める現代までの歴史を紐解く。
ウォーハンマーアーミーブックより
旧き者の訪れ
…それは時の黎明期。
今から遡ること数千年、あるいは数万年以上も前のこと。
高度な文明を持ち、「旧き者」の名だけで知られる種族が、遠く離れた彼らの世界から、星々の海を渡ってこの世界へと移り住んだ。
旧き者は「星の門」を造り、これを用いて別世界へと渡ったり、宇宙の最深部を自在に行き来したりできたという。
まさに神のような力を持つ彼らが、これから語るような行動をとったのはなぜか? 彼らの目的は何だったのか?
…この問いに答えられる者は、もはや誰もいない。
旧き者は、自分たちなしでも成り立つ世界を造り出そうとしていたのかもしれないし、いつの日か自分たちの文明とこの世界に生きる他種族たちに降り注ぐ「大災厄」を防ぐべく、彼らなりに手を尽くしていたのかもしれない。
ただ一つ明らかなことといえば、彼らの“大いなる計画”が成就されることはなかったということだけだ。
旧き者はまず、自らの力を使ってこの世界そのものを動かし、太陽へと近づけた。
より温暖な…つまり、彼らにとってより快適な気候を作り出すためだ。
続いて旧き者は、それぞれの大陸を彼らの望む形へと造り変え始めた。
この頃すでに、この世界には数多くの獣や、感覚をほとんど(あるいはまったく)持たないような怪物たちが暮らしていた。
これらの代表格が、ドラゴンである。
ドラゴン。この高い知性を持つ賢き生き物たちは、旧き者と取引をし、ほんのわずかではあるが、彼らから魔法的な知恵の数々を学び取った。
もっとも、すべてのドラゴンがそうだったわけではない。
ドラゴンの多くは旧き者との関わりを避け、山脈の地下や大海原の底といった暗い場所に隠れ住んでいたようだ。
かつては寒冷だった自分たちの世界が、あまりにも暑くなりすぎてしまったため、ドラゴンたちは数世紀にもおよぶ眠りにつかなくてはいけなくなったのである。
最初の種族たち
やがて旧き者は、新たな種族たちをこの世界へと住まわせ始めた。
初めに創造されたのが、スランである。
彼らは旧き者によって制御された「力」を使うことに、きわめて熟達していた。
旧き者はスランたちに大きな信頼を置き、彼らの都市を発展させることや、大海の流れを制御すること、そしてむき出しの岩から山脈を造ることなど、様々な仕事を任せてゆく。
 続いて旧き者は、スランの仕事を助けるためにリザードマンを創造した。
続いて旧き者は、スランの仕事を助けるためにリザードマンを創造した。
この爬虫類じみた戦士たちは、原始の密林をうろつく巨大な怪物どもからスランの土地を守るべく勇ましく戦い、巨大都市を建築する働き手の役目もになっていた。
加えてリザードマンたちの中には、書記や職人など、他にも様々な役目を果たす者たちがいたようだ。
次にあらわれたのが、エルフである。
彼らは生まれながらにして、旧き者が使う「力」…人間たちからは「魔法」と呼ばれる力…との間に強い繋がりをもっていた。
エルフたちの故郷とすべく、海の底からウルサーンの島が持ち上げられる。
ウルサーンの島で、旧き者とスランに見守られながら、エルフたちは魔法を学んでいった。
しかし、エルフたちが魔力のあつかい方を会得するにつれ、残念な事実も明らかになっていった。
エルフたちは、旧き者が期待していたよりも魔法に対する抵抗力が弱く、堕落しやすいことがわかったのだ。
この経験を活かし、旧き者はドワーフと呼ばれる次なる種族をこの世界に迎える。
ドワーフは頑丈で頼もしく、そして何よりも特筆すべきことに、魔法に対する強い耐性を持っていた。
ドワーフとエルフは、たがいの欠点を補い合うように創造された種族だったのだ。
ドワーフは職工の業を教えられ、最高の匠たちへと成長していった。
だが不運なことに、ドワーフもまた自らの欲望の前には無力であり、やすやすと堕落することがわかってしまう。
それは、ドワーフたちが時に「頑固さ」「強欲さ」「偏狭さ」などを美徳と考えることからも明らかだった。
若き種族たち
長い歴史の中。
いずこかの時点で、オークたちがこの世界へとやってきた。
これは予想にすぎないが、旧き者の乗る「星の船」によって、 恐ろしいオークの胞子が思いがけずこの世界に持ちこまれてしまったのかもしれないし、あるいはオークたちが自らの力で、虚空の中をただよいながらこの世界へとたどりついたのかも知れない。
どちらにせよ、その瞬間から、グリーンスキンたちは、この世界の他種族たちにとって大きな脅威となったのである。
次に迎えられたのが人間たちだ。
人間はドワーフやエルフとちがい、肉体的な強さや精神的な強さ、そして魔法をあつかう能力などを、まったく持ち合わせていなかった。
旧き者が、なぜ人間という不完全な種族を創造したのか、ある意味不思議にすら思える。
おそらく、人間は「未完成」だったのだろう。
かの大崩落がこの世界を襲った時も、人間たちはまだ洞穴の中で原始的な生活を営んでおり、言葉や国と呼べるものをほとんど持ち合わせていなかったのだから。
いずこかへと姿をくらます直前に、旧き者はハーフリングとオウガをこの世界に残した。
彼らは、魔法への耐性を持つ種族を創造しようとし続けた旧き者による、いわば「破れかぶれの最後の努力」と呼ぶにふさわしい二種族である。
確かにハーフリングは、肉体的にも精神的にも、魔法に対する強い耐性を持つ。
だが、あまりにも素直すぎるがゆえに、きわめて下品な性格を持つというどうしようもない欠点を持ち合わせてもいた。
また、巨体を揺らすオウガたちは、おどろくほど頑丈な体を持つにいたった。
だが、その反面、彼らの頭の悪さや不器用さ、そして好戦的な性格はひどいものだった。
どうやら旧き者も、妥協せざるを得なかったようだ…。
ドワーフ帝国の興り
エルフたちがウルサーンの島にとどまり、旧き者から教えを乞うことに満足していたいっぽう、ドワーフたちは自分たちが育った山脈沿いに、世界を北へ北へと旅していた。
彼らドワーフの始祖たちは、世界の底にある鉱物を掘り当てるべく、岩々を深く掘り進みながら進んでいたのだ。
彼らの愛するものは、大空の下ではなく、いつも地の底にあったからである。
ドワーフは武器や機械づくりで名をあげたが、むろん、旧き者が持っていた超技術の数々と比べれば、お遊びにも等しいものであった。
それでもドワーフは、匠の業を大いに磨き続け、それにともなってドワーフ帝国も成長を続けていったのだ。
やがてドワーフたちは、最果て山脈に移り住む。
そしてここを中心に、要塞都市の数々を長大な地下道網で結んでいった。
地下道は金銀の装飾によって彩られ、それらが魔法のラン夕ンによって美しく照らし出されていたという。
エルフがついに魔法を極めるころ、ドワーフたちも旧き者の智彗をもとにして、ルーンの秘術をあみだしていた。
ルーンの力によって、彼らは強大なる力を宿した武器や、決して壊れぬ鎧を鍛え上げられるようになったのだ。
かくしてドワーフの匠たちは、自身すらも魅了してしまうような、魅力的な品々を次々とつくり上げていった。
それとともに、ドワーフたちは富に対する愛情をますます強めていったが、この時点でまだ彼らは、鉱物の採掘と職工の腕前を磨くことだけで十分満足していたようだ。
少なくともこの頃、この世界の各種族は、この上なく幸多き時代を過ごしていたといえる。
そう、まもなく訪れる不和の時代のことなど、知るよしもなく…。
混沌の襲来
この世界に息づく種族たちは、平和を満喫する暇もなく、大きな危機に直面した。
旧き者の使っていた門が、突如として崩落したのである。
その原因は、まったくもって明らかになっていない。
だがおそらく、この大崩落を引き起こしたのは、旧き者自身だったのではないだろうか。
どうやら、門の向こうに広がる不定形の次元から、実体を持たぬ怪物たちがこの世界へと攻撃をしかけてきていたらしいのだ。
門の先にある「悪夢のごとき世界」からの侵攻を防ぐために、旧き名は、やむなく自らの手で門を崩落させたのである。
門の崩落にともない、生なる魔力によって空前絶後の大爆発が引き起こされた。
その光が空を覆い、猛烈な波動が山々と大海原を揺るがす。
二つの極点が内側に向かって崩壊したことで、世界を満たすエーテルの中に、生なる魔力が溢れ出してしまったのだ。
この時から、ワープストーンと呼ばれる純粋な混沌の結晶である天体が、世界の周囲を旋回するようにして飛び周り始めた。
今日でもなお、この天体の破片はときおり地上へと降り注ぎ、不吉な形の岩となって発見されている。
大崩落に前後して、旧き者はいずこかへと姿を消した。
彼らがこの世界から逃げ出したのか、それとも大崩落によって滅んでしまったのかは、どの記録を紐解いても語られていない。
ただ、一つわかっているのは、これ以降、彼らがこの世界を歩むことはなかった、という事実だけだ。
もっとも、スランたちの多くは、「いつの日にか時が満ちれば、旧き者はこの世界へと戻ってってくるであろう」との預言を残してもいる…。
門の崩落と同時に、オールド・ワールドを膨大な魔力が駆け巡った。…そして、混沌が産声をあげる。
天は燃え、地は激しく揺れた。
この世界に暮らしていた種族たちの原初の恐怖や悪夢が次々と実体化し続ける中、魔力の業火の中から、ついに恐るべき暗黒神たちが産み出されたのだ。
定めある命しか持たぬ者、すなわち定命の者ちが抱く激しい惜念によって実在を与えられた暗黒神らは、すぐにエルフ、人間、ドワーフの国々に気づき、これらをむさぼろうと画策するようになった。
混沌の怪物どもが初めてこの世界に姿を現したのも、この天変地異のさなかである。
ヒポグリフ、シマエラァ、マンティコア、グリフォンなどを筆頭とする怪物たちが、我が者顔で大地をのし歩いた。
彼らは本来、この世界に息づくまっとうな生き物だったが、魔力によって歪められてしまったのである。
かくして生まれ落ちた混沌の怪物たちにより、徐々に世界は毒されだした。
ビーストマン、すなわち獣人が産声をあげたのもこの時だ。
ある者は、内に秘めた「動物的な欲望」をさらけ出すかのように獣じみた姿へと歪められた堕落した人間たちであり、またある者は、変異の果てに後脚で立ち上がり、人間のように地を歩むようになった獣たちである。
のちにティリアが建国される大沼沢地の北部では、ずる賢い知性を持つ歪んだ鼠人間たちが、地に穴を掘って潜み始めた。
そして彼らは誰にも知られることも、見られることなく、世界の地下を掘り進み、暗い陰謀を企て始めたのだ。
そして、誕生したばかりの混沌の暗黒神たちは、オールド・ワールドに対して初めての大規模な侵攻を開始した。
実態を持たぬ悪魔のごとき怪物どもが、崩落した北極点の門から次々と溢れ出してくる。
怪物の巨大さたるや、これまでこの世界を歩んだいかなる生き物をも凌駕するほどであった。
さらに世界は、激しい魔力の波動によってなめつくされた。
それゆえに、暗黒神に仕えるディーモンたちは、思うがままにこの世界を歩むことができたのである。
ディーモンの兵団は地をなめつくし、エルフたちの住むウルサーンの島にまで迫った。
ここで、世界の運命を決する一戦が幕を開けようとしていた。
エルフたちが敗北すれば、混沌はオールド・ワールドを完全に吞みこむだろう。
そしてエルフたちが勝利すれば、世界は破滅の運命を免れるのだ……少なくとも一時の間だけは。
エルフの払った犠牲
エルフたちを危機から救ったのは、アナリオンに率いられたエルフのメイジたちであった。
アナリオンはウルサーンの初代不死鳥王であり、現在では「守護者」の名とともに語られる伝説の存在である。
この偉大なるエルフの戦士は、輝きの島に安置された古の武具「力インの剣」を抜き放ち、その大いなる力よってディーモンの大軍を次々に屠ったのだ。
ただ悲劇的にも、戦神カインその人のために鍛えられたとされる、この呪わしき剣を振るったことにより、混沌の穢れがアナリオンの血の中に焼き付けられてしまっていた。
アナリオンにかけられた呪いは、今日でも尚、彼の末裔たちを猟犬のごとく執拗に追い続けている。
アナリオンと彼の軍は、勝利に次ぐ勝利を重ねていたが、それでもなお悪夢のごとき怪物の大津波は、とどまるところを知らずエルフたちの王国を襲っていた。
エルフの中でもっとも賢い者たちは、「この戦争によって自分たちが破滅するのは明らかである」と悟っていた。
いかに強大なるウルサーン軍といえども、永遠に戦い絞けることなどできないからだ。
そこで、空を翔る竜騎士たちの助けを得たアナリオンの大軍は、ディーモンたちの大軍勢に対抗すベく、「死の島」の守りを固めることにすべてをかけた。
かの島では、カレドール君に率いられたエルフたちが、大いなる儀式を執り行おうとしていたのである。
故郷たる島が沈没するかも知れないと知りながら、それでもなおエルフたちは、世界を破滅から救おうとした。
そして、魔力の大渦をつくり出すために、死の島に神秘的なストーンサークルが築かれたのである。
大渦は、オールド・ワールド中に荒々しく吹きすさぶ魔力の風を吸い込んでいった。
自分たちを定命の者の世界につなぎとめていた魔力が渦の中に吸い込まれるや、ディーモンの軍勢は総崩れを起こし始める。
これを次々と討ちはらってゆくアナリオン。
だが、この激しい戦いの中で、彼自身もまた致命傷を追って息絶えた。
この時以来、ストーンサークルから放散しなければならない膨大な魔力によって、ウルサーンは絶えず崩壊の危機にさらされ続けてきた。
エルフたちは、かつての世界のほうがより魔法的であったと語る。
それは事実だ。
魔力の大部分は、ウルサーンのストーンサークルの中へと吸い込まれてしまったのだから。
はるか昔にあみ出された魔法の品々や魔術の数々を、この世界で再びつくり出すことは、もはや不可能なのである…。
かくして、混沌による最初の侵攻が退けられると、エルフたちは変わり果てた世界の探索に乗り出した。
その中で,彼らはドワーフとの運命的な出会いを果たす。
こうしてエルフとドワーフの間で交易が始まる頃、原始的な人間の祖先たちも、世界中に移り住んでいた。
この頃の人間たちは、自分たちがこの大いなる二大文明によって護られていることなど、微塵も知らなかったようだ。
いつの日かこの世界に、三種族の間で混沌に対抗するための大いなる同盟が結ばれる時がやってくるかも知れない。
だが、それはあってはならぬことでもあった。
別離の時代
アナリオン王の後妻モラスィが産んだナガリィンのメルキ王子は、歴史上もっとも偉大なエルフへと成長していた。
メルキスは並ぶものなき将となり、彼に率いられたエルフの軍勢は、世界のあちこちで混沌の大軍勢を打ち払っていったのである。
また、メルキスは公正明大かつ辛抱強い姿勢でドワーフとの交渉にのぞみ、彼らの至高王である”白髭”スノーリ公と友情を深めた。
そしてこの二人の友情をもとに、エルフとドワーフは、この世界にはびこる暗黒の怪物たちを山脈のほら穴や暗い森の奥底へと追いやるための、大同盟を築きあげたのだ。
しかし、メルキスの心にも、渾沌の穢れは息づいていた。
ただこの時はまだ、彼の心奥に隠されていただけのことだ。
エルフの貴族たちから嫉妬を受け続けたメルキスは、いつしか、不自然なまでの権力欲と野心を抱くようになっていった。
そして、不死鳥王の座を熱望し始めたのである。
そのため、ヴェルシャマールの君が彼を差し置いて不死鳥王に即位すると、メルキスの心の中で煮えたぎるような憎悪が生まれ、それはヴェルシャマール王の暗殺をメルキスに決意させた…。
かくしてメルキスは「ヴェルシャマール公が、混沌の暗黒神を信奉しておられる」と、虚偽の告発をおこなった。
この直後、毒によって死亡した不死烏王ヴェルシャマールの遺体が発見されると「 メルキスは「王はみずからの堕落を罰せられることを恐れ、毒を飲んでその命を絶たれたのだろう」と述べ、エルフたちは誰一人としてこれを疑わなかったという。
首尾よく政敵を始末したメルキスは、ついに不死鳥王の座を自らのものとした。
そして、かつて父もそうしたように、自らが神々に祝福されし者であることを証明すべく、アシュリアン神殿の聖なる炎の中へと足を路み入れたのだ。
しかし、聖なる炎はメルキスを拒絶した。
彼の全身は聖なる炎に焼かれ、醜い火傷跡よって覆われてしまったのだ。
そしてこの日から、メルキスの身体は苦痛によってさいなまれることとなった。
かくしてメルキスの裏切りが明るみに出ると、かつて彼の支持者であったエルフたちは武器をとり、一斉に彼の敵にまわった。
哀しき「別離の時代」の訪れである。
エルフたちは互いに殺し合い美しきウルサーンの島は強大な魔法によって無残に引き裂かれていった。
血で血を洗う内戦の中、メルキスに従う者たちは、その魂を次第に毒されてゆく。
彼らの心はねじまがり、ただ一つの事柄に異常なまでの執着を見せるようになった。
同族への復讐である。
尊大なるメルキスは、他の者たちを操るのと同じように混沌の軍勢を意のままに操り、みずからの目的のために使役できると確信していた。
彼がこのような考えにいたったのは「旧き者の正統なる後継者であるエルフは、この世界を支配すべく運命づけられている」と信じていたためだ。
だが、 メルキスはこの戦いに破れて海の彼方へと追放され、荒涼とした暗黒大陸ナーガロスへと落ちのびた。
そしてメルキスと彼に率いられたダークエルフたちは、世界の諸勢力が一致団結して混沌の侵攻にあらがうという希望を、粉々に打ち砕いていったのである。
世界の運命を決したのは、エルフたちの別離だけではなかった。
ドワーフとエルフの間には、かつて結んだ強固な同盟がなお存在していたが、彼らはいまや世界を二分する大勢力となっており、互いに”最終的には敵対することになろう”とみなし始めていたのだ。
そしてやっかいなことに、彼らの持つ文化や性格は、お互いまったく正反対だったのである。
そしてついに、旧き者がこの世界を離れて以来、もっとも大きな悲劇が起こってしまった。
邪悪なるダークエルフたちがドワーフをだまし討ちしたことにより、エルフとドワーフという二つの巨大な勢力は、激しい争いを始めてしまったのである。
事の真実はこうだった。
ドワーフの交易船を襲ったのはダークエルフの略奪隊だったが、ドワーフから見れば、エルフが友好の誓いを破ったとしか思えなかったのである。
しかも高慢なるハイエルフたちは、謝罪を求めるドワーフの大使たちの髭をそり落とし、宮廷の外へと放り出したのだ。
頑固なドワーフたちは、もともとエルフたちに抱いていた嫌悪感をついに爆発させ、もはや後戻りのきかない対立へと向かってしまったのである。
かくして巻き起こった「髭戦争」 (ドワーフたちは、復讐戦争と呼ぶことを好む)は、数百年もの長きにわたって続けられ、両種族にとって癒えぬ傷痕を残した。
そしてこの長い戦争り中で、エルフとドワーフは世界中に広げていた互いの国土を縮小し、みずからの本国へと引きあげざるをえなくなってしまう。
もっとも、これが人間の文明の発展につながったわけだが、それは同時に、荒野にひそむものどもを再び野放しにする結果にもなった……すなわち、不死者、オーク、ゴブリン、トロール、そして混沌の怪物たちが、再び地上へ戻ってきたのだ。
それからわずか数百年の間に、オールド・ワールドは、危険に満ちあふれた場所へと変わり果ててしまう。
そこは、現在よりもなお危険な世界だった。
エルフとドワーフが互いの傷を癒すことにかかりきりになっている間、人間たちは、周囲を圧倒的な数の敵によって取り囲まれることになって しまったのである。
よみがえる死者たち
この頃、新たな文明がその曙を迎えていた。
南方の地ら住む人間の部族が、砂漠に大きな街を築きはじめたのが、この文明のはじまりだったようだ。
もしかすると人間たちは、大陸の南に広がる大密林の中で、旧き者たちが築いた太古の神殿都市を目にしていたのかもしれない。
彼らの王国は、その最盛期において悪たれ平原(バッドランド)のさらに北まで広がった。
歴史上存在したいかなる人間の国家も、この古代王国の比ではない。
自らの国を、彼らはネフェキーラと呼んだ。
オークや獣人(ビーストマン)たちが北方の森をめぐって争いを繰り広げる中、南方の人間たちは大いに栄え、その数を増やしていった。
何世紀も時間をかけながら、ネフェキーラの熱砂の大地に、いくつもの王国が乱立したのだ。
諸王国は交易を行い、またあるときには戦争を繰り広げ、この砂漠を支配する争いをいつ果てるともなく続けていた。
そして今から時を遡ること五千年前、この大砂漠に偉大な都が誕生した。
司祭王セトラその人によって治められし王都、クェムリである。
セトラ王は並ぶものなき猛将であるとともに、恐ろしいほど強い自尊心をもつ人物だった。
それゆえ、彼はみずからの支配をおびやかす、いかなる者の存在をも許さなかったという。
使者をとおしてセトラ王への臣従を要求する書状が他の国王たちに送られる中、この偉大なるクェムリの支配名は、自らの軍勢を率いて戦いを挑み、勝利に次ぐ勝利を重ねていった。
大砂漠に点在する他の都は、一つまた一つとクェムリの同盟国となり、そうでないものは、セトラ王自身の手によって滅ぼされていったのだ。
だが、この世の栄華をほこるセトラ王にも、打ち倒せない敵が一つだけあった。
“死”である。
彼は祭司団に「朕の輝かしき威光を永遠のものとせよ」と命じ、みずからの寿命を延ばすため、ありとあらゆる手段を講じさせた。
祭司団は、セトラ王の命を延ばすために長大なる儀式をいくつも考案したが、彼らの力をもってしても、死の訪れを食い止めることはかなわなかった。
かくしてセトラ王が死の眠りについたとき、祭司団は王の亡骸を永久に保存すべく、大儀式をとりおこなった。
数千年後か、あるいは数万後か、セトラ王が死の眠りから覚め、不死の生とともにこの世に復活することを願って…。
セトラの崩御後、続く五百年間にわたって、クエムリとネフェキーラはその富をおおいに減じた。
かつての同盟国はしだいにクエムリから離れ、ふたたび都同士の争いがくり広げられたのだ。
また、セトラ王の前例にならって、歴代のネフェキーラの統治者たちも、冷たい”死の掌握”から逃れる手段を探すことに強くとりつかれていった。
そしてこの努力は次第に形を変えてゆき、高い社会階層に位置する者たちがピラミッドを築いて死後の躯を復活の時まで保存することに心血を注ぐようになるまで、それほど時間はかからなかった。
あらゆる都の近隣には、巨大な”死者の都市(ネクロポリス)”が築かれ、そこには生者の住まう家々よりも、はるかに大きな逮物が建ち並んでいたという。
そして、死者の都市に眠る死者たちの人数は、次第に生者たちの人数を上回っていったのだ。
ナガッシュ
セトラの治世が終わりを告げてから、およそ五世紀後。
ネフェキーラの地に、強火な力を持つ一人の人間が生まれた。
時のクエムリ祭司王の兄弟、ナガッシュである。
ナガッシュは並ぶものなき埋葬儀式の知識をほこっていたが、彼をもってしてもなお、死者を蘇らせることはできないでいた。
彼が抱いていた定命の生に対する恐怖や強迫観念は異常なほどで、それはかつて永遠の生を求めたセトラ王の情熱をはるかに超えるほど強いものであったという。
そのため、彼は不死の秘密を解き明かすべく、ありとあらゆる手をつくしていた。
もちろん彼身も膨大な研究を続けていたが、死霊術の名でも知られる、かの忌まわしき魔術が完成をみたのは、思いがけぬ客人との出会いがきっかけだった。
ネフェキーラ湾で座礁したダークエルフの一団が、ネフエキーラ人によって捕えられたのだ。
この機会を見逃すナガッシュではなかった。
彼はダークエルフたちから暗黒の魔術体系の謎を引き出し、この知識をもとにして、死霊術をあみだしたのである。
ナガッシュは下僕たちの血を用いて研究を重ね、ついに”生命のエリクシル”と呼ばれる秘薬を造り出す。
そして、この秘薬によって、みずからの身体を維持し続けることに成功したのだ。
超自然的な長命を得たナガッシュは、兄弟である祭司王になりすまし、”不死”という名の甘い誘惑によって家臣たちを自らの下僕に変えながら、少しずつその力を蓄えていった。
そしてこの裏切りの祭司は、強大な魔力の風をとらえ、自らの魔力をさらに増すために、”漆黒のピラミッド”を建造せよと命じたのだ。
恐るべき力を手にしたナガッシュとその下僕たちは、血に飢えた神のごとく、クェムリの人々を恐怖のくびきにつなぎとめた。
だが、ナガッシュの行動は、次第に他都市をおさめる祭司王の注意を引いてゆく。
そして祭司王たちは、力を強め続けるナガッシュの存在を危険視し、これに対抗すべく団結を始めた。
そしてついに、祭司王ラーミザールによって率いられた祭司王の連合軍クェムリを攻め、強大なる死霊術師ナガッシュを、漆黒のピラミッドの中へと追い詰めた。
ナガッシュの配下たちはすべて捕えられ処刑されたが、ナガッシュ本人の死体だけは決して発見されなかったという。
ナガッシュがすでに戦いの中で滅んだものと信じる祭司王たちは、すぐに同盟を解消し、再び大砂漠の覇権をめぐる争いを再開した。
そして、忌まわしいナガッシュの記憶は、次第に風化していったのだ。
吸血鬼の誕生
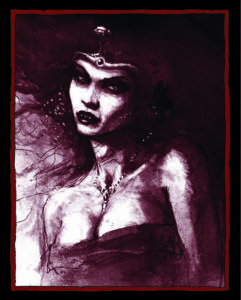 だがしかし、人間はナガッシュの遺産が放つ誘惑に打ち勝つことはできなかった。
だがしかし、人間はナガッシュの遺産が放つ誘惑に打ち勝つことはできなかった。
ラーミアの都をおさめる女王ネフェラタは、司祭王間の取り決めを破り、禁じられたナガッシュの墳墓へと足を踏み入れたのだ。
ネフェラタは、ここでナガッシュが残した禁書の数々を発見し、みずからの都へと持ち帰ることに成功する。
彼女は、ナガッシュの”生命のエリクシル”を、自らの手で再び造り出そうとしていたのだ。
そしてこの試みは、不完全な形で成功してしまう。
確かに、彼女は不死の躯を得た。
だがそれは非常に不完全なものであり、彼女は猛烈な渇きにさいなまれるようになってしまったのだ。
そう、人間の血を吸うことでしか癒せない、禁断の渴きに…。
ネフェラタは下僕の血を吸わなくては不死の存在を維持できない躯になっていた。
そしてまた、彼女の宮廷に集う者たちも、次第に吸血の呪いによって毒されていったのだ。かつてナガッシュが祭司王らの注意を引きすぎ、行動を起こさせた時と同じように、ラーミアの都もまた、妖しげな血の儀式にまつわる不吉な噂がついてまわるようになった。
吸血鬼と化したラーミアの支配者たちが、残された不死の秘密を解き明かそうと躍起になっている頃、かのナガッシュの魂は、砂漠や荒れ野をさまよっていた。
実体を失い、なかば発狂した彼の魂は、辛酸の海をふちどる海岸線にそって北上し、片欠け峰のある大山脈へとたどりついた。
ここで彼は、途方もない量のワープストーン…すなわち、生なる魔力が形をなしたもの…を発見する。
ワープストーンの力を用いて死霊術の力をさらに増したナガッシュは、太古の戦場に眠る骸骨の戦士たちを次々と蘇らせる。
そして、これらの不死者を奴隷として操り、巨大な地下迷宮”ナガシュザール”を建造させたのだ。
また彼はこの頃、同じくワープストーンに引き寄せられてきたスケイブンとも、長い争いをくり広げた。
だが最終的にナガッシュは、混沌に汚染されたこの鼠人間たちとの間に、暗き密約を取り交わすことに成功する。
ここへきてようやく、ラーミアの吸血鬼たちはナガッシュの復活に気づいた。
ナガッシュと交渉すべく、吸血鬼たちは使者や密使を次々と送り込んだが、間もなくして、悲劇的な事実が明らかにされる。
死霊術のとりことなった吸血鬼たちは、知らず知らずのうちに、ナガッシュの奴隸となり果てていたのだ。
もはや彼らは、この偉大なる死霊術師の命ずるままに動くしかなかった。
吸血鬼の助力を得たナガッシュは、いよいよ憎き祭司王らに対して、大戦争を引き起こす。ナガッシュと彼の吸血鬼は、かつて自分たちに忠誠を誓いながらも、その後に彼らを追放したネフェキーラの民を、押び支配しようと画策していたのだ。
亡者の戦争
二度とナガッシュの奴隷になどなりたくなかったネフェキーラ人は、団結して死者の侵攻へと立ち向かった。
十年以上にもおよぶ、長い戦争の始まりだった。
ナガッシュと彼の吸血鬼たちは、ネフェキーラ軍を激しく攻める。
しかし、ネフェキーラ軍を率いていたのは、セトラの治世以来、随一の司祭王とうたわれた”征服王”アルカディザールであった。
彼は死者の軍勢を打ち負かし、大砂漠のほうぼうへと四敗させたのだ。

しかしまたしても、ナガッシュは難を逃れていた。
彼は報復とばかりに、死の疫病をネフェキーラの地に蔓延させる。
病で死んだ数千人の民は歩く死者となって蘇り、続々とナガッシュの軍勢に加わっていった。
勢いやまぬ死者兵団の前に、さしものアルカディザール王も撤退する。
そしてアルカディザール王自身もまた敵の手で捕らえられ、地下迷宮ナガシュザールで幽閉されてしまったのだ。
かくしてネフェキーラ軍を破ったナガッシュは、”大蘇り”の儀式を実行に移した。
大量のワープストーンから膨大な魔力をしぼりつくした後、彼はその魔力をすべて用いて、空前絶後の呪文を解き放ったのだ。
それは、この世界で用いられた暗き魔法の中で、もっとも強大なものであった。
猛烈な負の波動が、ネフェキーラ全土をかけめぐる。
生者は活力を失って朽ち果て、逆に死者は眠りから引き起こされ、墳墓の中より歩み出た。
 だが同じ頃。
だが同じ頃。
片欠け岬のスケイブンたちは、ナガッシュとの同盟を破棄しようと企んでいた。
そして、邪魔なナガッシュを自分たちの手を汚さずに消すため、ずる賢い策略をめぐらせていたのだ。
かくしてスケイブンたちは、残忍なる刃と名付けられた強大な武器を緞え上げた。
ワープストーンを材料として造られた、恐るべき魔剣である。
そしてスケイブンらは、ナガシュザールに囚われていたアルカディザールの手に残忍なる刃を与えて檻から逃がし、彼をナガッシュのもとへと導いたのだ。
アルカディザールは、”大蘇り”が完成する直前、ナガッシュの手を切り飛ばして儀式を中断させた。
ただちに、両者は激しい争いを始める。
本人は知らないままだったが、スケイブンの妖術によって支えられるアルカディザールは、残忍なる刃を用いて、ついにナガッシュの肉体を滅ぼした。
その後アルカディザールは、ナガシュザールから脱出すべく戦い続ける。
しかし、彼の肉体と魂はすでに、残忍なる刃に秘められた穢らわしい混沌のカによって焼かれていたらしい。
哀れ、アルカディザールは盲目河へとまっさかさまに転落し、溺れ死んだ。
かくして”大蘇り”の儀式は中断したが、それでもなおナガッシュの放った強大な呪文は、オールド・ワールドを完全に、そして永遠に変えてしまっていた。
砂の下に葬られていた司祭王とその軍勢が、偽りの生とともにこの世へと還ってきていたのだ。
墳墓王となったかつての司祭王らは、みずからの墳墓から這い出ると、生前と同じく、再び互いに戦争をくりひろげた。
亡者の戦争である。
だがそれも、”不滅なる”セトラ王が蘇るまでのことだった。
もっとも強大にして、もっとも古き祭司王、”不滅なる”セトラ。
彼はかつてのように、ふたたび数々の都を意のままに従えると、自らを不完全な形で眠りから引きずり起こしたナガッシュに対し、永遠の復讐を誓った。
なぜなら、セトラたちの躯は、不死なる黄金によって置き替えられた輝かしき肉体などではなく、埋葬された当時の薄汚い骸布によってくるまれ、暗き魔術によって身もだえする程に、みすぼらしく枯れ果てた骸の躯だったのだから…。
一方、ナガッシュは斃されこそしたが、その脱心である吸血鬼の始祖たちは墳墓王の追っ手から逃げのびていた。
一部の吸血鬼は北へ落ちのびたようだ。
北の地では、まだほら穴から出てきたばかりの人間の部族たちが、ようやく小屋や村を造り始めた頃だった。
また他の吸血鬼は、東へ、南へと、めいめいの方角へと散っていったという。
そして、ナガッシュ本人もまた復活をとげていた。
残忍なる刃の魔力をもってしても、彼を永遠に葬り去ることはできなかったのである。
彼はふたたび生者の世界を支配しようとたくらみ、産声をあげたばかりのシグマーの帝国に対して牙をむいた。
この痛ましい戦争は、ふたたび世界の運命を大きく変えることになってしまう。
だが、この戦争については、また別の機会に語るとしよう…。
ドワーフをみまった災難
エルフたちがドワーフとの戦争に敗れ、オールドワールドを去ってから、六十年の月日が流れようとするころ…。
ドワーフ帝国は、激しい天変地異にみまわれていた。
最果て山脈は大地震によって激しく揺れ動き、引き裂かれ、噴火によってあふれ出た溶岩が、灼熱の大河を形づくった。
ドワーフの要塞都市も大地震に揺れ、山脈の地下に築かれた大広間が、いくつも崩落していった。
さらに、ドワーフの砦町や要塞都市をつなぐ広大な地下道網……ドワーフ語で呼ぶところ
のウングドリン=アンコル……もまた、各地で落盤を起こし、ところどころで寸断されてしまったのだ。
地下道網の破壊。
それは世界中に点在する要塞都市が孤立することを意味していた。
さらに、大規模な地殼変動によって大混乱におちいったドワーフたちは、外敵の侵攻をやすやすと許してしまう。
中でも、髭戦争以来ドワーフたちの主敵となっていたオークとゴブリンは、山脈をうめつくす大軍勢となって、ドワーフの要塞都市へと押し寄せてきたのだ。
最初に陥落した要塞都市は、ナイトゴブリンの侵略を受けた、北の果ての大都カラク=ウンゴルであった。
百万にも達するグリーンスキンの大群は、大都にたてこもるドワーフたちを包囲し、何ヶ月にもおよぶ激しい戦争をくり広げた。
そしてついにドワーフたちは、住み慣れた地下の大広間と坑道を追われ、荒野へと追い出されてしまったのだ。
カラク=ウンゴルは、ゴブリンやスケイブンといった暗黒の怪物たちがうごめく場所へと変わり、赤眼山と呼ばれるようになった。
これを手初めとして、いくつもの鉱山や要塞都市が、敵の手に落ちていった。
かつては難攻不落で知られた大都の数々も、オーク、オウガ、トロールをはじめとする怪物たちによって、好き放題に襲撃されてしまったのだ。
そして、かの”白銀街道の戦い”が始まった。
銀槍山の鉱脈を守り抜こうとするドワーフと、大族長ウルク=グリムファングに率いられたオークたちの間で、激しい戦争が巻き起こったのだ。
しかし、銀槍山の守りはついに破られ、その征服者の名を取って、グリムファング山と改名される事になってしまった。
そしてこれは同時に、最果て山脈の東の山肌におけるドワーフの領土が、完全に失われたことをも意味していた。
からくも難を逃れた数千人のドワーフたちは、失意の中、なおも残る要塞都市へと落ちのびていった…。
ゴブリン戦争
かくして東部の要塞都市群を失い、西に残る要塞都市へと落ち延びたドワーフたちだったが、これらの要塞都市もまた、およそ千年間にわたって外敵に包囲され、激しい攻撃にさらされ続けることになった。
これらの要塞都市をめぐる一連の戦いを、ドワーフたちは”ゴブリン戦争”と呼んでいる。
もっとも、敵はゴブリンばかりではなかった。
スケイブンや獣人(ビーストマン)といった邪悪なものどももまた、これらの戦いの中でドワー
フに死をもたらしたのだ。
カラク=エイトビークでは、ドワーフの造った広間や公道のさらに地中深くに、スケイブンの地下道網が広がっていることがわかった。
それから二百年もの間、ドワーフたちは地底からの侵略に対して、苦しい戦いを強いられた後、無念の敗北を喫している。
スケイブンが恐るべき毒の風を通路という通路にまき散らしたところへ、ゴブリンの大軍が襲いかかってきたのだ。
それまでオークやゴブリンの猛攻に耐えてきた大都のひとつ、カラク=アズガルもまた、カラク=エイ卜ビークでドワーフたちが敗北した直後に、陥落の憂き目を見る。
ここで勝利をおさめたグリーンスキンたちは、その勢いに乗じてカラク=ドラズにまで攻めのぼり、これを圧倒した。
大都カラク=アズールと至高王の座す白都カラザ=カラクもまた、怒りに満ちたグリーンスキンたちの猛攻にさらされたものの、両都がどうにか持ちこたえたのは、不幸中の幸いである。
しかし、栄華をほこったドワーフ帝国がいまや没落の途をたどっているのは、誰の目から見ても明らかだった。
戦争も後半にさしかかり、外敵の侵略を耐え抜いたドワーフの要塞都市も、昔日の栄光の影をわずかに残すのみとなったころ。
ドワーフたちは、人間の部族との同盟を熱望するようになっていった。
その頃の人間たちは、最果て山脈の西に広がる森林地帯で、しだいに力をつけはじめていたのだ。
そして、ある一人の人間とドワーフとの間に結ばれた友情が、その後二千五百年間にもわたり彼らの運命を、大きく変えることとなる…。
人間の時代
はるか遠きキャセイやインドゥアの地、そして北方の大草原や、果ては混沌の荒れ野にいたるまで。
数百年もの年月をかけて、人間たちは世界のいたるところへと移り住んでいった。
彼らがすみかを求めた地の中で、尊大海と最果て山脈の間に広がる地は、後にオールド・ワールドと呼ばれることとなる。
ネフェキーラのような一部の例外をのぞけば、夜明けを迎えたばかりの人間の文明はどれも、小さな部族によって形づくられる小規模なものばかりだった。
ほら穴の中や木で作った小屋に暮す人間の小部族がオールド・ワールドの各地に点在し、山や森で狩りをしながら生活を営んでいたという。
そして彼らは、手つかずの深山や広大な森にひそむ獣人(ビーストマン)やゴブリンといった邪悪な外敵から身を守るため、苦しい戦いを強いられていたのだ。
だが、偉大なる戦士王にして人間の指導者たるシグマーの誕生により、すべてが変わった。彼は後に”エンパイア”の名で知られ、今日もなお栄える人間の大帝国を築き上げた男である。
 ウンべローゲン族長の長子として産まれたシグマーは、少年時代からすでにその頭角をあらわしはじめていた。
ウンべローゲン族長の長子として産まれたシグマーは、少年時代からすでにその頭角をあらわしはじめていた。
十五歳になるとき、彼はすでに有能な狩人にして勇ましき戦士として名を知られていたのだ。
そんな彼がある日、灰色山脈のふもとを旅していたドワーフの一団がオークによって捕えられていたところにでくわしたのも、おそらくある種の宿命だったのだろう。
彼が救い出したドワーフの一団には、まぎれもなくドワーフの至高王”鉄鬚”クルガン公の姿があった。
この偉大なるドワーフの指導者は、シグマーに返礼として強大なルーンハンマーを贈る。
これこそが“ガールマラッツ”髑髏砕きの名を持つ、偉大なるウォーハンマーであった。
シグマーはガールマラッツをたずさえて、数えきれないほどの戦に赴き、勝利に次ぐ勝利を収めた。
この若者は、これまで人間たちを食い物にしていた恐ろしい敵を、ガールマラッツの一撃で次々と打ち砕いていったのだ。
連戦連勝を続けるシグマーの軍。
その姿に多くの人間が勇気づけられた。
そしていつしかガールマラッツは、シグマーその人の象徴となったのである。
またシグマーは、グリーンスキンだけでなく、渾沌の勢力と手を結んで北方から攻め寄せてくる人間の部族が、自分たちの平和をおびやかしていることをよく理解していた。
そして、これらの敵に対抗するため、彼は国づくりに遇進した。
戦士王シグマーが見た夢。
それは、強い指導者のもと、団結力にあふれる国家をつくることであった。
シグマーは、現在エンパイアとして知られる国家の礎を築きはじめたのである。
数々の交渉と合戦を経て、シグマーは後にエンパイアとなる地に暮らしていた人間の諸部族をまとめあげ、一大連合国家を作り上げることに成功する。
いまや、最果て山脈の西と灰色山脈の北に広がる地は、シグマーの名のもとに統率されていた。
もちろん、暗い闇の奥底では、獣人(ビーストマン)やフォレストゴブリンなどがなおもひそみ続けていたが、これら外敵によって明日をおびやかされる危険きわまりない日々から、人間たちはようやく解放されたのである。
もっとも、まだ最後の大合戦が残されてはいた。
黒火峠の戦いである。
シグマーに従う人間の諸部族は、頼もしき同盟相手である”鉄鬚”クルガン公のドワーフ軍とともに、悪たれ平原(バッドランド)から北へと攻め寄せてくるグリーンスキンの大群を、かの黒火峠で迎え討ったのだ。
グリーンスキンたちの人数たるやすさまじく、黒火峠からこれを見下ろす人間たちの目には、その大軍の終わりがどこで果てるとも知れず続いていたという。
激しい合戦が始まった。
そして手痛い犠牲を払いながらも、ついに人間とドワーフの同盟軍は勝利をおさめる。
かくして、西方におけるオークの勢力は、完全に粉砕されたのである。
シグマーの帝国
黒火峠の戦いで勝利をおさめたシグマーの帝国は、その後数十年間にわたり、これまでない平和な年月を過ごした。
シグマーに従い、黒火峠で勇ましく戦った人間の族長たちのために、”鉄鬚”クルガン公は偉大なる篆刻鍛治(ルーンスミス)”狂える者”アラリックに命じ、十二本の魔剣ルーンファングを鍛えさせた。
長年の時を経てようやく完成した時、ルーンファングが帝国大貴族にとって権威の象徴として用いられるようになったのはこのためだ。
それから五十年間にわたって、シグマーはみずからの帝国をよく治めた。
八十歳になってもなお、彼は強く壮健であり続けたという。
そう、シグマーの力は一向におとろえることなく、むしろその賢さにみがきがかけられてきていたのだ。…だというのに、シグマーはまだ若く弱いエンパイアを彼に従った族長たちに託して、みずから皇帝の座を退いたのである。
帝冠を脱ぎ、一人の戦士に戻ったシグマーは、供もつけずに東方へと旅立った。
彼は旧友である”鉄鬚”クルガン公に会いにいったのだという説もあれば、最果て山脈を越え、不浄ヶ原のグリーンスキンどもに戦いを挑みにいったのだという説もある。
しかし、真実は定かではない。
あとに残された族長たちは、皇帝の座をめぐって互いに血みどろの戦いをくり広げることのないように、ある名案を考えつく。
それは、自分たちの中でもっとも皇帝にふさわしいと思える者に対し、族長たちがみずから票を投じ、自分たちの中から皇帝を選出することだった。
それから数世紀の間、エンパイアは発展を続けてゆく。
小さかった村々は、立派な町や強大な都市へと成長し、かつての族長たちの末商は、取り決めにしたがって自分たちの中から歴代の皇帝を選び、民をよく導いた。
また彼らは、自分たちが皇帝の選定権をもつことから、その称号を選帝侯、すなわちエレクター・カウントと改めたのである。
ドワーフの匠から手ほどきを受け、エンパイアの職に人や建築家たちも、めざましい成長をとげる。
そしてもちろん、友情によって結ばれた二国間の同盟も、さらに強固なものに育っていった。
また、エンパイアに暮す臣民たちが、初代泉帝シグマーを神として信仰し始め、各地に天主シグマーを讃える大教会が建築されていったもこの頃だったという。
だが、平和な時代にも終わりが訪れる。
権力欲と野心におぼれた選帝侯の子孫らは、やがてあい争うようになったのだ。
そしてこの隙を見逃さず、昼なお暗き森の奥で、あるいは光届かぬ地の底で、エンパイアの敵は密かに力を蓄えていった…。
 恐ろしい疫病がエンパイアに蔓延するのと時を同じくして、鼠のごとき姿を持つスケイブンの軍勢が一斉に地地底の穴から討って出た。
恐ろしい疫病がエンパイアに蔓延するのと時を同じくして、鼠のごとき姿を持つスケイブンの軍勢が一斉に地地底の穴から討って出た。
そしてスケイブンたちはエンパイアの村々を襲い、そこに暮す村人たち奴隷にしたのだ。
これを迎え撃つはずの選帝侯の軍勢も、スケイブンによってまきちらされた伝染病によって、大きく力を減じてしまっていた。
そして、長き内戦によって分裂したエンパイアに、スケイブンを撃退するだけの力はもはや残されていないかに思われた……まさにその時だった。
ミッドンランド選帝侯マンドレッド伯が、大軍勢をまとめあげて反撃を開始したのだ。
エンパイアの農場や村々から追いはらわれたスケイブンは、ふたたびもとの地底世界へと戻っていった。
新たな指導者マンドレッド伯のもとに終結した選帝侯たちは、迷うことなく彼を次なる皇帝として選出し、それから数年間の間で、エンパイアは復興の兆しを見せ始める。
しかし、狡猾なるスケイブンたちがおとなしく引き下がるはずもない。
彼らは最後のあがきとばかりに、エンパイアに対して痛烈な一撃をみまったのだ。
スケイブンを支配する”十三人の魔王”らの放った暗殺者が、マンドレッド帝の暗殺に成功したのである。
選帝侯たちは混乱におちいり、皇帝の座をめぐる暗闘がふたたび始まってしまう。
裏切りや暗殺が、政治の舞台でまたも横行するようになったのだ。
三皇帝時代
マンドレッド帝暗殺から百年の間、選帝侯たちは権力欲におぼれ,エンパイアでは”骨肉の内戦と陰謀劇が続いた。
富と権力のことしか頭にない貴族たちに率いられ、人間たちの軍勢が互いにせめぎ合いを続けた結果、シグマーの残した偉大なる帝国は千々に引き裂かれてしまう。
多くの者が選帝侯の座を求めて名乗りをあげ、選帝侯による皇帝選挙制度は完全に隅へと追いやられたのだ。
数世紀にわたる醜い内戦の後に訪れたのが、分裂の極めつけである。
かの悪名高き”三皇帝時代”である。
むろん、内戦によって国が乱れている間も、エンパイアはつねに外敵の攻撃にさらされ続けていた。
選帝侯はみずからの州軍だけでこれを撃退することはできず、同盟相手たちに助力をこうのが通例だった。
そんな中、エンパイア全土を舞台として、最初の大規模な合戦が巻き起こる。
強大なるオーク大族長”鈎爪の”ゴルバッドが、黒火峠を越え、エンパイア南部の諸州を踏みにじりながら恐るべき勢いで攻めのぼってきたのだ。
ソランド選帝侯領は、オークたちによって略奪のかぎりをつくされた後で、跡形もなく焼きはらわれていた。
しかも、この戦いの中でソランド選帝侯その人までもがゴルバッドの手にかかって殺害され、そのルーンファングすらも奪われたのである。
 そこからウイッセンランド州と独立都市ナルンを荒らし回ったゴルバッドの大軍勢は、ついにレイクランドへとなだれ込み、アルトドルフ市門に対する攻城戦を開始した。
そこからウイッセンランド州と独立都市ナルンを荒らし回ったゴルバッドの大軍勢は、ついにレイクランドへとなだれ込み、アルトドルフ市門に対する攻城戦を開始した。
レイクランド選帝侯すらもが激戦の中で戦死したが、それでもなお打ち倒せないほど、ゴルバッドは強大な族長だったのである。
もっとも、レイクランド伯の死は無駄ではなかった。
彼らが身をていして市門を守り続けたために、攻城戦は異例の長期戦となり、その中でグリーンスキンたちは生来のまとまりのなさを見せ始めたのだ。
オークの大群はいくつもの小集団に分かれて内輪もめを始め、やがて散り散りに引き上げていったという。
ところが,ゴルバッドとの戦いが終わると、選帝侯たちは再び権力争いを始めてしまう。
それから三百年間に渡って内戦が続き、エンパイアは混乱をきわめた。
そして、人間の帝国を狙う次なる脅威が鎌首をもたげたのである。
ここへ来てついに選帝侯たちは、積年の不和を忘れ、ふたたび一致団結して帝国の敵に立ち向かわねばならなかった。
というのも、いまや陰気な森と不死者たちがうごめく墓地により、オールド・ワールドでもっとも悪名高い地となり下がったズィルヴァニア選帝侯領から、皇帝の座を求めて新たな権力者が名乗りをあげたからだ。…時のズィルヴァニア選帝侯、ヴラド・フォン・カーシュタイン伯爵である。
 恐るべきことに、ヴラドは定命の者ではなかった。
恐るべきことに、ヴラドは定命の者ではなかった。
彼は最初の吸血鬼伯爵だったのだ。
彼が吸血鬼の始祖の一人だったのか、それとも、吸血鬼の呪われた血脈に連なる者だったのかはわからない。
いずれにせよ、ヴラドがまず狙いを定めたのは、オストマルクとスターランドであった。
ヴラドによって率いられた不死者の軍勢は、およそ四十年間もの長きにわたってエンパイアを攻め続ける。
これが、のちに吸血鬼戦争と呼ばれる過酷な戦争であった。
さらにヴラドは、アルトドルフをも攻めた。
この強大なる吸血鬼を滅ぼしエンパイアを救ったのは、時のシグマー教団総主教、ヴィルヘルム3世である。
総主教はヴラドと市門上で激しい戦いをくり広げた後、ヴラドの身体をはがいじめにし、もろとも地面へと身を投げたのだ。
市門前に並ぶ防柵の杭につらぬかれ、ヴィルへルム3世とヴラドは杜絶な最後をとげた。
だが、ヴラドの死をもってしてもなお、吸血鬼の脅威は去らなかった。
ヴラドの呪わしき子らが、エンパイアに対してさらに激しい攻擎を、 数十年間にわたって続けたからである。
また、吸血鬼戦争とほぼ時を同じくし、選帝侯らの身勝手な行動によって引き起こされた別の大事件が、エンパイアをゆるがしていた。
巨大な彗星が、オストマルクの首都であるモードへイムの都市を直撃したのだ。
さらに彗星は、穢らわしく拍動する混沌の魔力をモードへイムに残した。
廃墟へと変わり果てた街に、ワープストーンの破片が容赦なく降り注いだのである。
その魔力を手にすることが、どれほど深刻な堕落につながるのかを知りもしないまま、ワープストーンに興味をひかれたありとあらゆる者たちが、モードへイムの廃墟に軍勢や傭兵団を送り込んだ。
最終的にこの街は、エンパイアの騎士団と、シグマー教団総教主の直命を受けた魔狩人らによって浄化され、モードへイムの廃墟はあとかたもなく破壊された。
だが今でもなお、モードへイムのあった場所は禁忌の地として悪名高い。
混沌の穢れは、かの地に今なお深く染み付いているのだ。
混沌大戦
その後、エンパイアは数えきれないほどの戦争を経験し、そのたびに、絶体絶命の危機をどうにか切り抜けていた。
不安定きわまりない情勢の中でも、人間の帝国は直面した脅威をすべて退け続けてきたのだ。
迫り来る危機は次から次へと深刻になっている。
だが、それでもなお、エンパイアはつねに多大な犠牲をはらってこれらの戦いに勝利してきたのだ。
これら数々の戦争の中でも、”大戦”の名で呼ばれるものはただ一つしかない。……それが、混沌大戦だ。
この時代、北の果つるところでは、混沌の領域がその力をこれまでにないほど増大させていた。
混沌の暗き影は南へと向かってにじみ出し、そこに広がっていた荒れ地の数々をのみこんでいったのだ。
抗うことを許さず押し寄せる、混沌の大波……その先駆けとなって侵攻してきたのは、混沌に仕える恐るべき従者たちであった。
北の荒れ野からさまよい出た怪物の群れに、トロール郷の周辺からあらわれた混沌の戦士の戦旅団が次々と流を果たす。
そしてエンパイアを覆う暗い森の奥底では、獣人(ビーストマン)らが集い、戦支度を着々整えていた。
影が南へと広がるにつれ、混沌はその勢力をさらに増していったのである。
そして帝国暦2303年の冬。
リンスク河にかかる橋を守っていたキスレヴ軍は、北方から押し寄せてきた混沌の大軍勢によって押しつぶされた。
この戦いの中で、何人もの混沌の”統べる者”たちが、恐るベき名声を勝ち取った。
だが、これら猛将の名中でも、混沌に立ち向かう者たちからもっとも恐れられていた総大将は、”統べる者”アサヴァール・クルをおいて他にない。
 野蛮きわまるクルガン族の族長であるクルは、恐れ知らずの戦士であるとともに、抜け目ない指導であり、さらには熱狂的な暗黒神の崇拝者でもあった。
野蛮きわまるクルガン族の族長であるクルは、恐れ知らずの戦士であるとともに、抜け目ない指導であり、さらには熱狂的な暗黒神の崇拝者でもあった。
彼が軍を率いて赴く先には、例外なく恐怖と死がついてまわったという。
クルのもとに集った混沌の大軍勢はあまりにも膨大で、もはや一人の人間が指揮できる規模をはるかに超えていた。
このためクルは混沌の怪物たちの大群をいくつかに分けると、彼に従う何人もの”統べる者”たちに、それらの指揮をゆだねたのである。
もちろん、これらの”統べる者”たちは、例外なくアサヴァール・クルの旗印を掲げて戦った。
クルの大軍勢によって最初の標的とされたのが、キスレヴ北部の守りを固める都市、プラーグであった。
歪みきった獣、悪魔のごとき怪物、そして狂乱した野蛮なる戦士たちは、プラーグの市門を何日間にもわたって攻め続ける。
キスレヴ軍も激しい反撃をくり広げ、プラーグ市門前には混沌の軍勢屍がうずたかく積み上げられていったが、それでも彼らの攻めの手は止むことはなかった。
そして、キスレヴ軍たちの疲労がきわみに達し、これ以上防戦を続けられない状態になると、混沌の大軍勢は一気にこれを押しつぶし、プラーグを蹂躙する。
中でも痛烈だったのは、プラーグに対するとどめの大攻勢において放たれた、混沌の妖術であろう。
この妖術によって、プラーグには永遠に癒されることのない混沌の傷跡が残ってしまった。……今日でもなおプラーグは、無数の怨霊たちの声が響き渡り、市壁が奇怪にうごめき、病んだ不死者たちが徘徊する、穢れた禁断の地として知られているのだ。
プラーグを陥とした混沌の大軍勢は、首都キスレヴへとまっしぐらに進軍する。
キスレヴを治める時のツァーリ(女皇帝)も手をこまねいて見ていたわけではない。
彼女はエンパイアに何度も使者を送り、友邦の援軍を信じていた。
だが、選帝侯たちは迫りくる混沌の脅威から目をそむけ、みずからの利己的な野心だけを追い続けていたため、女帝からの悲痛な書状は、そのほとんどがないがしろにされてしまったのである。
この時、独立都市ナルンでは、マグナスと呼ばれる一人の若者が熱弁をふるっていた。
「シグマーの子らよ、ともに立ち上がるときは今ぞ! 我ら集いて、混沌の進行に立ち向かうひとつの軍とならん!」と、彼は情熱的な演説を突続け、多くの帝国臣民を奮起させたのだ。
マグナスの声は臣民らの胸をうち、勇気と愛国の気持ちを与えた。
天主シグマーの御国を守るための義勇軍が結成されるまで、それほど時間はいらなかった。
さしもの選帝侯たちも、ナルンに集い始めたこの軍勢を無視することはできなかったようだ。彼らは競争相手である他の選帝侯におくれを取るものかと、競うようにしてマグナス支持を表明し、大規投な州軍をマグナスの軍に加えるべく送り出し始めたのである。
一方その頃。
最果て山脈に築かれたドワーフの大都カラザ=カラクでも、ドワーフの至高王が迫りくる混沌の脅威を察していた。
そして至高王は、キスレヴの助太刀に駆けつけるべく、みずから総軍を率いて出陣したのである。
到着した至高王とその軍は、キスレヴにて熱烈な歓迎を受ける。
ドワーフたちはその人数こそ少なかったものの、屈強にして恐れ知らずの武人ぞろいであり、キスレヴの都に広がり始めていた不安や動揺をしずめるために、多くの力添えをしたという。
マグナスの軍が北へ向け進軍を始めた頃、混沌の大軍勢はいよいよキスレヴ総攻撃に取りかかった。
壮絶なキスレヴ攻城戦が、いよいよを開ける。
アサヴァール・クルに率いられた”統べる者”とその大軍勢は、キスレヴの守りをこじ開けようと、容赦ない攻撃をくり返したという。
キスレヴの市壁を打ち崩すべく、大悪魔たちが次々に突進してくる。
大悪魔の強大さたるや、至高王に率いられたドワーフの豪族たちをも苦戦させるほどの、恐るべき相手であった。
さらに市壁へは、化け物のように巨大な攻城兵器から発射された岩や大矢が次々と降り注ぎ、強大な魔法の炎が浴びせられ始める。
キスレヴとドワーフの連合軍が混沌の猛攻に押され始めたその時、思いがけぬ援軍が現れた。
ハイエルフである。
永きにわたって、オールドワールドの地をこれほどまでに大規模なハイエルフの兵団が歩むことはなかった。
ウルサーンの”すべてを知る者”の中でもっとも偉大なるテクリス師が、ハイエルフの兵団を率いて、キスレヴ救援へとおもむいたのだ。
ハイエルフの優美なる純白の船団は、鈎爪湾の岸へと次々に到着を果たす。
一糸乱れぬ足取りでオールドワールドの大地に降り立つハイエルフの光輝なる兵団、宿敵混沌との決戦にのぞむ準備を完全に整えていた。
兵団の一部はミッドンへイムの砦から出陣しようとしているマグナス軍に合流し、残る者たちは一路キスレヴへと向かった。
かくして、キスレヴ市門前の攻城戦は、オールド・ワールドの歴史上もっとも壮絶な戦いへと発展した。
人間、悪魔、エルフ、獣人(ビーストマン)、ドワーフ、そして混沌の戦士たちが入り乱れる血みどろの合戦は、実に数日もの間、かたときも休むことなく続けられたのだ。
アサヴァール・クルを頭目とする、暗黒神の寵愛を受けた強大なる”統べる者”たちは、人間とエルフとドワーフの連合軍を次々に打ち倒していったが、勝利の栄光を勝ち取ったのは彼らではなかった。
時は、プラーグ陥落前にさかのぼる。
マグナスはプラーグを救うべく、いくつもの騎士団からなる混成軍を北へとさしむけていた。しかし無念にも、彼らはあと一歩のところでプラーグ救援に間に合わず、南へと取って返していたのだ。
北方からなおも進軍してくる混沌の残党を追いながら、ひたすら南へと進む道中、騎士たちはキスレヴ軍の生き残りと合流を果たす。
そして今、彼らがついにキスレヴ市門前へと到着し、カルの軍勢の後方をついたのである。騎士たちは骨をも砕く激しい突撃をくりだし、混沌の軍勢を一気に引き裂いていった。
この機に乗じ、キスレヴの守りにあたっていた連合軍も一斉に討って出る。三方面から一度に攻撃を受けた混沌の大軍勢は、完膚なきまでに打ち碎かれた。
伝説によれば、クルを討ち取ったのはマグナスその人であったという。
とはいえ、これはいささか信憑性にとぼしい。
というのも、マグナス自身は戦士としてよりも、たぐいまれなる指導者として名高い人物だったからだ。
彼が本当に、ほとんど不死に近い混沌の従者であるクルを打ち倒すことができたのだろうか?
真実はわからない。
結局のところ、クルの死体すら発見されていないのだから。
だが少なくとも、クルが討ち死にしたのは間違いないだろう。
渾沌の大軍勢は、散り散りになって逃げていったのだから。
大戦は終わった。
だが、北方からの脅威が無くなったわけではない。
北方人の戦旅団は、しばしばキスレヴやエンパイアを襲い、狼藉のかぎりをつくし続け、森はまだ暗いままであった。
カール・フランツ帝の御代
キスレヴ市門前の戦いの後、混沌の勢力は次第におとろえていった。
悪魔たちは再び混沌の領域へと引き下がり、闇はオールド・ワールドの地から払われていったのだ。
混沌によって歪められたプラーグの廃墟は、跡形もなく打ち壊された後で、その上に再び都市が築かれた。
だが、この地に染みついた混沌の穢れはあまりにも強かった。
それゆえ、プラーグは今でもなお不吉なる都市としてその名を知られている。
また、エンパイアをふたたび一つにまとめあげた功績を称えられた”敬度なる”マグナスは、選帝侯らの推薦をうけ、正式な選出皇帝の座についた。
マグナス公はすぐに、エンパイアの森の中になおもひそむ獣人(ビーストマン)の討伐にとりかかる。
これにより、オストランドやオストマルクに暮す帝国臣民は、獣人(ビーストマン)恐怖から次第に解放されていった。
混沌の諸勢力も、トロール郷か、あるいはさらに北方まで退くことを余儀なくされる。
かくして、オールドワールドに平和が訪れた。
混沌大戦がもたらしたオールドワールドへの影響も、この頃になって次第にあらわれはじめる。
その際たるものが、テクリスに率いられたハイエルフのオールドワールド再探訪であろう。
さらにテクリスは、帝立魔法大学校の創設に力を貸した。
この出来事をとおして、ウルサーンのエルフとエンパイアの人間たちの間で、互いの理解が深まったのは間違いない。
そしてこの時すでにエンパイアは、エルフとドワーフの両者から教えをこう者であるとともに、苦い過去を引きずる彼らの間に立って、お互いの仲を取り持つ役目を果たすようにもなっていた。
いつの日か来る混沌に対する最終戦争で、エルフやドワーフとともに、人間もまた大きな役割を果たすことだろう。
混沌大戦の後、エンパイアは偉大な皇帝のもとで団結し、再び世界における一大勢力としての国力を取りもどしていった。
またマグナス公は、彼の出身都市であるナルンを飾っていた鷹獅子の彫像群にちなみ、”鷹獅子帝”の名で呼ばれた最初の皇帝でもある。
もっとも、それほど時を経ずして、大いなるレイク河の流れにいだかれたアルトドルフの宮へと、帝宮は戻されることになった。
それから何世代にもわたって、皇帝の座は歴代のアルトドルフ大君によって引きつがれるようになった。帝都アルトドルフの玉座に座し、これらの皇帝たちはエンパイアを統治し続けてきたのだ。
そして記念すべき帝国歴2502年、時のレイクランド選帝侯にしてアルトドルフ大君でもあるカール・フランツが、現帝国皇帝に即位した。
その後、数年間の統治の中で、彼は自らが強く勇敢なる指導者であることを証明してみせている。
エンパイアは今なお数々の外敵によって国土を脅かされてはいるものの、カール・フランツ帝は初代皇帝シグマーと”敬度なる”マグナス公によって残された大いなる遺産をよく治めている。
事実カール・フランツ帝は、オールドワールド稀代の指導者として高い名声を勝ち得ている。
また、彼はありとあらゆる手段をつくし、エンパイアの諸選帝侯領や実力者たちを団結させ続け、国外の諸勢力と強固な同盟を結ぶことに力を傾けるすぐれた外交家でもある。



コメント